2023/4/15
こんにちは。
オチャノマ文具店のちょこです。
お米って美味しいですよね。
松本に来て初めて、本当の新米を食べて、もちもちで甘くてうるうるな美味しさに激しく感動。
すっかりお米好きになってしまいました。

筆者:choco(ちょこ)
都会から松本に移住して8年。
介護福祉士として働きながらシェアハウスで5年間を過ごす。
田舎の日常をまったり発信。

いろんなお米の話。
我が家では、白米、玄米、黒米(古代米)、雑穀米、などなど、その日の気分でごはんを炊きます。
白米以外のお米は少し消化しにくかったりもするので、半分とか3分の1を白米に混ぜて炊いています。
それぞれ違った風味で、塩を振るだけでも美味しくいただけます。

玄米などは白米よりも食物繊維やビタミンB群など豊富らしいので、食事の栄養バランスを考えるのが楽ちんになりました。
手抜きおかずしかない時でも、とりあえずごはん食べとけば大丈夫!って思って気にしないでいられるのがいい。

うちには炊飯器がなくて、ごはんは必ず土鍋で炊きます。
土鍋ごはんの美味しさを知ったら、もう炊飯器には戻れません。
同じお米でも全然味が違うのでぜひ一度は試してみて欲しい。
味以外にも、土鍋の方が早く炊けるということと、洗うパーツが少なくて済むということと、省スペースになるというも、土鍋炊きを選んでいる理由です。
せっかくなので、我が家流の土鍋ごはんの炊き方も紹介しておきますね。
我が家流土鍋でごはんを炊く方法
土鍋でごはんを炊くのって、めっちゃ楽ちん。
コンロは火力が強いので、炊飯器より短時間で炊きあがります。
ここで紹介する炊き方はわたしが8年間くらい土鍋炊きで生活してみて習得した方法です。
一般的かどうかはわからないし、専門家には怒られるデタラメな方法かも。
でも、美味しく炊けてます。

①お米をしっかり浸水させる
土鍋ごはんを炊くのにいちばん大切なのは、しっかりお米を浸水させておくこと。
我が家では最低40分~1時間くらい浸けておきます。
お米が水を吸ってふっくらした状態を知っておけば、時間を測らなくても見れば炊き時がわかるようになります。
玄米などは白米よりも長く浸水させる方が柔らかくなって美味しいので、お米の特徴に合わせて浸水させる時間も変えます。
土鍋は水をたっぷり吸った状態で火にかけると割れてしまうことがあるので、浸水はボールで行うのが良いです。
②中火で沸騰させる
我が家はいつも2.5合炊き。
硬く炊きたいときは水加減は450ml。柔らかめが好きなわたしはたっぷりの水(指の第一関節+@くらい)で炊くことも多いです。
土鍋を火にかけたら、フタをして、最初は中火くらいの火にかけます。
しばらく様子を見ながら待機して、ぼこぼこと沸騰させます。
②ごく弱火にする
ぼこぼこと沸騰したら、今度は最弱火にします。
このとき、へらなどでお鍋の底に張り付いたお米を剝がすようにかき混ぜます。こうすると底のお米だけが焦げるのを防げる(と思っている)。
弱火にしても、土鍋は保温性が高いので沸騰したような状態が続きます。
吹きこぼれるのが気になるので、たまにふたを開けて空気を抜きます。
本当はふたを開けてはいけないらしいですが、コンロがどろどろになるので…
炊飯用の土鍋だと、吹いても外にこぼれないような形状になっているのでいつか使ってみたい。
③音と匂いを聞く
耳を澄ませて、パチパチという音がし始めたら土鍋の中の水分が残りわずかになった証拠。
音を聞きながら鼻もきかせて…湯気の中に焦げたような香ばしい匂いがし始めた瞬間に火を止めます。
④20分蒸らす
火を止めたらそのまま20分蒸らします。
蒸らしの工程は、浸水の次に大事な作業。絶対に省いてはいけません。
天地返しをして、食べる
20分待ったら、天地返しをしてごはんを軽くほぐせば食べられます。
炊飯器で炊く場合も同じですが、鍋の底の方が水分が多い状態なので、天地返しをすると全体の水分量が整います。やらなくてもいいけど、そうやっておいた方が後で食べるときに美味しいです。
お米と水の量によって多少変わりますが、土鍋ごはんは大体15分くらいで炊けます。火を止めたあとは放っておけばいいので手間がかかりません。
家を出るときにお米を浸水させておいて、帰ってきてすぐ炊けば、その後蒸らしながらお風呂に入って、炊き立てごはんが食べられます。
内蓋を洗ったりする必要もないし、忙しい人にこそ向いている炊き方だと思っています。
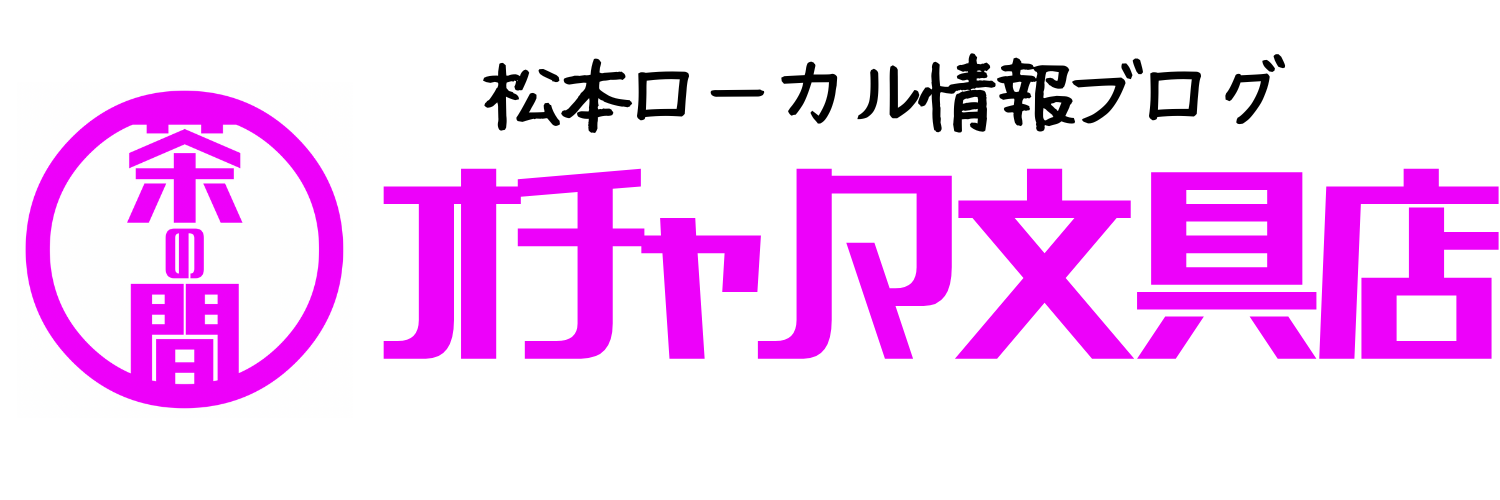



コメント