こんにちは。
オチャノマ文具店のちょこです。
皆さんの地域では、大晦日はどんな風に過ごすでしょうか。
郷里では大掃除をして、普通の夕食を食べて、紅白見ながら年越しそば食べて翌日に備えて寝る、という感じでさらっと過ごしていました。
しかし移住してきた長野県の大晦日は驚愕の事態に…!!
今年は長野県のお家に嫁いだ私が、初めてのリアル信州大晦日に潜入して謎風習「おとしとり」に迫りました。

「おとしとり」とは
松本に移住してきた初めての年末。
こちら出身の友人に、「えっ、おとしとりって全国じゃないの?」と言われ初めてその存在を知りました。
おとしとり
一体何をすることなのか、理解するまでにしばらくかかりましたが、どうもこういうことらしい。
『大晦日に家族みんなでご馳走を食べまくって、年越しを祝う』
数え年では、年を越すとひとつ歳をとる、という考え方。
年を越す、ということは、歳をとる、ということと同じ意味なので、こういうふうに呼ばれるんでしょうか。
<おとしとりの使い方例>
「大晦日はおとしとりしなきゃいけないから胃を休めておこう」
「今度のおとしとりは何食べる?」
おとしとりに欠かせない食べ物
大鍋で作るすまし汁
大晦日当日、お家によって若干違いはあるようですが、大晦日からお正月まで食べる根菜のすまし汁を大鍋で大量に作ります。
旦那さんの実家では、長芋(里芋のことも)、人参、大根、ごぼう、なると、ネギ、三つ葉に、いりこで出汁を取って醤油味のすまし汁にします。
鶏肉などを入れるお家もあるそうです。

この汁は、大晦日から食べ始めて、年をまたいでお正月も食べ続けます。
焼き餅をここに入れて煮込んで、そのままお雑煮にもします。
なので、とにかく大量に作る必要があります。
ちなみに、信州ではお餅といえば四角い切り餅
大阪では丸餅が定番でしたが、こちらのスーパーでは丸餅はほとんど売られていませんね。

ブリ
出世魚であるブリや鮭もおとしとりの必須食材。
松本ではブリを食べる場合が多いようです。
海のない長野県では、新潟などで捕れた魚を塩漬けにして保存したものが年越しのご馳走だったそう。
今でもその名残で、ブリや鮭を食べる家がすごく多いです。
松本でよく見かける「塩丸イカ」という塩漬けになったイカも、保存の歴史から生まれたもの。
ブリや鮭は、ブリしゃぶにしたり塩焼きにしたりして食べる場合もあれば、お雑煮に入れる場合もあるようです。
豆腐寄せ

豆腐寄せ、というのは豆腐のかけらを寒天か何かで固めた食べ物。
砂糖と醤油の甘じょっぱい味。
お盆やお彼岸、年末になるとスーパーに陳列されます。
おせち
おせち。
お正月といえばおせちですが………
信州では信じられないことに、大晦日からおせちも食べます。

大晦日と元日の区別はない
お義父さんに聞いたところによると
「大晦日と元日って…別にあんまり区別はないなぁ」
とのこと。
この辺でようやくわかってきたのですが、「おとしとり」というのは大晦日のことではなくて、大晦日から元日までひっくるめて「年を越す」ということを指すんですね。

だから食べるものも大晦日、正月と区別せず、おとしとりで食べるものということになるから、お雑煮だっておせちだって大晦日から食べ始めちゃうわけです。
スーパーに並んでいた大量の酢タコや豆腐寄せも、大晦日から正月中食べるから1パックにあんなに大量に入っていたんです。
おせちに雑煮にブリにお刺身に、家によってはここにお寿司やピザが加わりご馳走もご馳走。
たらふく食べて歳をとることをみんなで盛大にお祝いするのがおとしとり。
二年参り
たらふく食べてゆく年くる年でも見たら、年が変わる前に神社に出かけます。
大晦日の深夜にお参りをして、そのまま年が変わって元日の0時過ぎにまたすぐお参りをすることを信州では「二年参り」と呼びます。
氷点下の凍みる寒さの中で神社の境内に足を踏み入れると、不思議と改まった気持ちになります。
神様に1年のお礼を言って、また新たに1年よろしくお願いしますとご挨拶して、ようやくみんな布団に入って休みます。
おわりに
信州には、今でも多くの風習が残っています。
都会では簡略化されていることの多い季節の行事や風習の多くが、令和の時代にもきちんと受け継がれています。
家族単位で行えるものもあれば、町会や地区単位で行われるものも。
ご近所付き合いや町会のお仕事なんかは、面倒で大変で、今の世代にはそぐわないという考え方もあるけれど、口伝えで残っていく風習は、やはりこういう面倒くささとともにあるのでしょう。
わたしもこうして松本に根をおろしたからには、これからひとつでも多くの風習を後世に残していきたいと思います。
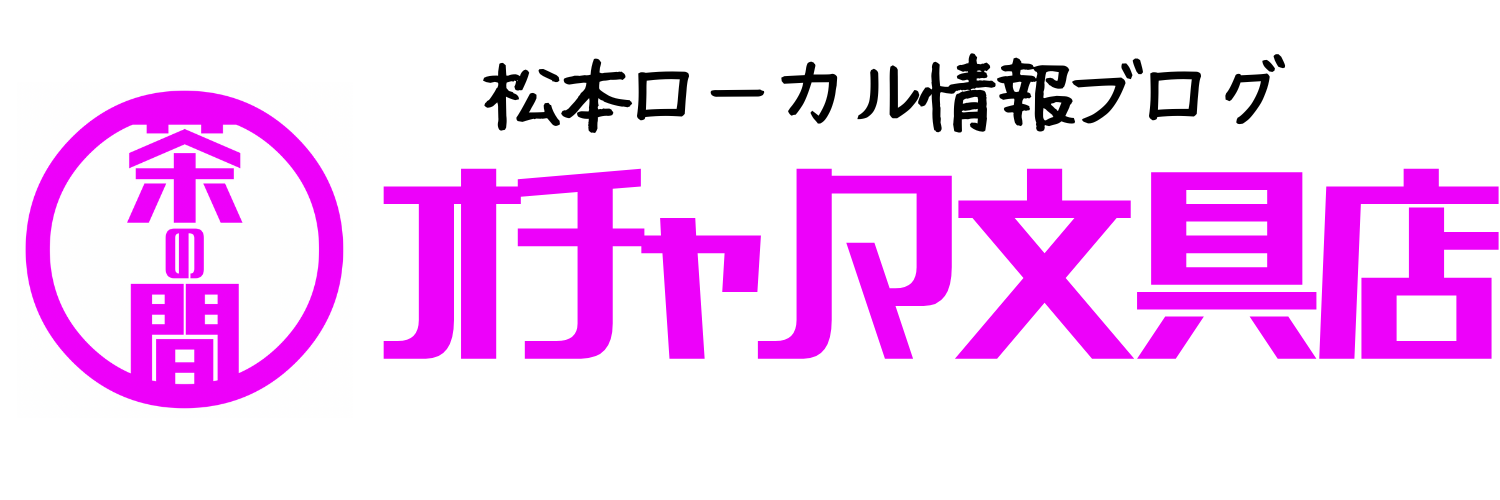



コメント