2023/10/13更新
こんにちは。
Chocoです。
大阪から松本に移住して5年を過ごしたシェアハウス「篶竹荘(スズタケ荘)」がある浅間温泉。
かつては路面電車が運んでくる宿泊客と芸者さんたちで賑わってそれはそれは栄えたそうな。
最近は側溝から湯気立ち昇るのんびり静かな温泉地と化していますが、1年に1度だけ、恐るべき夜が訪れます。
それが、奇祭「松明祭り」。
2023年もこの季節がやってきました!

筆者:choco(ちょこ)
都会から長野県松本市へ単身移住。
浅間温泉のシェアハウス生活を経て結婚。
マイルドな田舎暮らしをぼちぼち発信。
松明祭りには4回参加。

松明祭りとは
松明祭りとは、長野県松本市浅間温泉にある御射(みさ)神社の秋のお祭りのこと。
毎年10月の初旬の土曜日に行われます。
この秋のお祭りは夜行われる「宵祭り」と翌日朝から行われる「本祭り」に分かれていて、松明祭りとはこの「宵祭り」のことを指して呼ばれます。
「宵祭り」では、大小さまざまな燃える松明が浅間温泉街の中を引き回され、御射神社で燃え尽きます。


お祭りの意味
御射神社は温泉街ほど近くに春宮、三才山(みさやま)山中に秋宮(奥宮)があり、長い間狩猟と農耕の神社として祀られてきました。
御射神社の神様は、住民の生活安泰・五穀豊穣を守るため春になると秋宮から春宮に下りてきます。
そうして収穫の終わった秋、おつとめを終えた神様に煙にのって秋宮にお帰り頂く為に燃え盛る松明を奉納するお祭、これがこのお祭りの意味だそうです。

「浅間温泉に古くから伝わる奇祭「松明祭り」 むかしから生活安泰と五穀豊穣を祈願する浅間温泉の人々のため奥社より里へと降りてこられた氏神様を 秋の取り入れが終わると 人々は松明をたきその火煙にのせて奥社へお送りするという古くから伝わる行事とされています」
2023年の日程
2023年の松明祭りの日程は以下の通り。
松明祭り(宵祭り)
■10月14日(土)
16:45・・・神事
18:30・・・よさこい踊り
18:55・・・松明点火
19:00・・・松明出発(港の湯前)
20:00・・・奉納花火打ち上げ
本祭り、押鉾
■10月15日(日)
9:30・・・神事
10:30・・・押鉾出発
17:00・・・押鉾帰着予定
松明作り

松明祭りで引かれる松明は「連(れん)」という単位ごとに各自で作ります。
連は住民で作る町会の連だけでなく、幼稚園などの有志の連もあります。
伝統的な連には松明にこだわりがあって、「あの町会の松明はいちばん太い」とか「あの旅館の松明はいちばん高い」などという話を地元の方からよく聞きます。
オチャノマ文具店がある(2021年時点)シェアハウス「篶竹荘」のある町会は、浅間温泉でも一二を争う巨大松明を作ることで有名な連。
松明作りの主要メンバーはどなたも70歳を超えていますが、お祭りのある地域ならではの熱気と「今年もいちばん大きい松明を作るんだ…!!」という熱意には毎年圧倒されます。
大きな松明を作るには熟練の技術が必要です。
傾かずにしっかり立たせたり、火をつけたときにうまく燃えるようにしないと、当日途中で松明がばらけてしまったり、怪我をする危険もあるのでとても重要なことなのです。

松明の作り方
数年間参加させてもらって観察したところによると、作り方には2通りの方法があるようです。
① 差し込み方式
② のり巻き方式
①差し込み方式
藁を下から順に積み上げていきます。
土台となる一番下の段を作ったら、そこに藁を差し込んで次の段を作ります。
差し込み方にもコツがあるようですが、私にはまだわかりません。
差し込んだあとは、木槌で叩いてさらに押し込みます。
十分な量を差し込んだら、周りに太いワイヤーを巻いてぎゅうぎゅうにきつく縛ります。
たまに縦にしてトントンと地面に叩きつけて底が揃うようにしたり、斜めにならないよう傾きを確認しながら積み上げていきます。
周りを藁の紐でしっかり縛ったら(どの時点でこれをやるのだったか…)ワイヤーを外して完成です。
朝7時くらいから初めて、大体13時くらいまでかかって作ります。
この方式はかなり技術が必要なようで、毎年古株の師匠(スズタケではこう呼んでいた)が来て作り方の指導をしてくれていました。
最近は昔より藁が短くなった為(聞き込みの結果、これは機械で刈り取るようになったからという意見と品種の問題という意見に分かれている)、差し込み方式で作るのが難しくなったとのこと。
②のり巻き方式
地面にワイヤーを並べて、その上に藁を全て並べておいて、その名の通りのり巻きのように横からくるくる巻いて作ります。
こちらの方が短時間で楽に出来上がったような気がしましたが、大きいものを作る場合は崩れやすいので本当は差し込み方式の方がいいとの事。





まだまだ知らないことだらけでざっくりした情報ですみません。
今後も観察を続けます。
藁の確保
松明の材料は藁で、毎年農家さんから松明祭りの為に買い付けているそう。
(台風やコロナウイルスの影響で中止が続いた2019年~2021年も、お祭存続の為に藁の買い取りは続けていたとの事)
松明の保管
出来上がった松明は、毎年いつも同じ場所で保管されています。
多分町会ごとに保管場所が決まっているんだと思います。
松明は大体宵祭りの1~2週間前くらいに作られるので、完成した松明は当日までしばらく各保管場所で保管されることになります。
お祭り前の松明がある浅間温泉の風景も良いものです。



宵祭り(松明祭り)

宵祭りの始まり 点火
火が沈む頃、順番に松明に火が灯されていきます。



大きい松明は肩車して松明によじ登って点火します。
既に決起集会ですっかり出来上がっているおじちゃんたち。
色んな意味でどきどきします。


そこら中火事になりそうですが、後ろから消防隊の皆様がついててくれます。

松明の引き方
小さい松明に紐をつけて犬の散歩のように引きずる連もあれば、台車に乗せて楽々運ぶ連も。
大型の松明は、昔ながらの方法で運びます。
4~5人が松明を縛ってある紐を直接後ろ向きに背負うような恰好で持ち上げます。
(相当な力が必要なので大人の男性が担当することがほとんど)
松明からは綱引きのように紐を二本伸ばしておいて、前方から進路を定めながら各紐を残りの人数で引いていきます。
(これには子供や女性、見学に来た見知らぬ人が混ざることも)


前からの力だけで引くと、松明が前に倒れてしまうので、後ろからも引いています。
「ツールド・美ヶ原」という激坂自転車レースの会場になるほど、浅間温泉はきつい坂の多い町。
各パートが全力を尽くさないと、巨大な松明を動かすことはできません。
また、カーブを曲がる時には紐の引き方にコツがあり、指示を出すかけ声にも技術が必要です。
しかし昔はこの綱引き紐はなかったというから驚きです…。

最後まで運びきるために
松明は、御射神社まで引いて奉納しなければなりません。
途中で燃え尽きてしまっては元も子もないので、水をかけて燃えすぎないようくすぶらせたり、逆に火が消えないように空気を吹き込んで火を大きくしたりと…火の管理も大変。

火がついている上の方からだんだん燃えて目減りしてきます。
松明の作り方が甘いと、途中で崩れてしまうので作り方はやはり大事なわけです。
奉納花火
20時頃になると、奉納花火が打ち上げられます。
いつもは三才山(みさやま)山中で打ち上げられていたそうですが、前回開催時に見えなかったとかなんとかという理由で2022年は本郷(ほんごう)小学校の校庭から打ち上げられたそうです。

天気と中止
松明祭りが行われる10月初旬は、例年台風が接近する時期で天気が悪いのが普通。
2019年は大型台風の影響で中止となりましたが、地元の方に聞いたところによると、「自分が知っている限りは中止になったことは一度もない。雨が降ってもやる。」との事。
さらに続いてコロナウイルスの影響で2020年、2021年も中止に。
奇祭に挑む心構えと必需品
先一年の無病息災を祈って、なぜか松明の煤で顔を黒く塗られるのが恒例の火祭り。
煤と煙で鼻の穴から耳の穴まで真っ黒になります。
(私は松明祭用に毎年捨ててもいい靴と服を準備しておきます)
煙が凄まじく、目や喉に沁みて息もできないので、口を覆う手ぬぐいも必需品。
街中に煤が降るので、見学しているだけでも服が煤まみれに。
家の窓を開けっぱなしにしていたり、外に洗濯物を干していると悲惨なことになります。

浅間温泉街全部を巻き込む大イベントで、冗談ではなく火事場の真っ只中のような騒然とした様子に…。
日本三大奇祭と呼ばれるのも頷けます…。
初めて参加した年はあまりの狂気的な光景に呆然としたものです。
しかし実際に参加してみるとわかりますが、火を見ると人間って興奮するんですね。
旅館の前では万歳三唱して繁栄を祈り、お返しに振る舞い酒をいただくとさらに気分は高揚。
これが癖になってなにかおかしいと思いながらも毎年参加してしまうのです。
宵祭りの終わり 奉納
最後は長く急な坂を上って、御射神社の境内でぼうぼうと燃え盛る炎の中にすべての松明を投げ入れ奉納すれば神事は終了です。
終盤ではとっぷりと日が暮れています。

大体21:30くらいまでに全ての松明が奉納されます。


当日、道の両側には屋台が立ち並び、狭い道を燃える松明が駆け上がっていきます↓

↓最後はこの左手に松明を放りこみ、燃やして奉納完了です。



全ての松明が通り過ぎると、家に残って見物していた住人たちが家の前の燃えカスや残骸を箒で掃き清めます。

あんなに騒がしかった浅間温泉の街は、嘘みたいな静けさ。
焼けた匂いだけが、お祭りがあったことを夢ではなかったと教えてくれます。
一夜明け、本祭り
宵祭りの翌日。
日が昇ると焼け跡みたいにそこら中が真っ黒になっているのがわかります。
(しばらく町中から芳ばしい匂いが取れないので雨が降るのが待ち遠しい)
前夜の疲れが取れぬまま、朝8時集合で本祭りが始まります。
春宮の本殿で神事を執り行った後、押鉾(おしぼこ)さんと呼ばれるみこしを担ぎ出します。
「おたーちー」の掛け声のあと、本殿の周りを二周回って、神社を出発。


この押鉾さんも珍しい形をしているのでぜひご覧になって頂きたいもののひとつです。

毎年この時期は10度前後に冷え込むことが多いのですが、なぜこんな寒そうな衣装なのでしょうか…。

押し鉾さんが通るときに家の前で待っていると、「のっこばから参りました」と書かれた紙が付いたすすきをもらうことができます。
以下書き起こし
「のっこば」から参りました
今から およそ 六五〇年前よりのことです。
御射神社の奥社 三才山は 諏訪大社の日帰り猟場の最北端にあたります。
のっこば は「乗越場」と書き 御射神社の 奥社のある所を言います。
縁起ものだそうで、スズタケ荘では1年玄関に飾っていました。
かけ声いろいろ
押し鉾さんをかついで、一行は夕方まで旅館やお世話になった家で厄除けや商売繁盛を祈ってまわります。
各家の前では「商売繁盛!」の先導さんの声に続いて「わっしょいわっしょい!」さらに先導さんの「無病息災!」に続いて「わっしょわっしょい!」という感じでかけ声をかけました。
先導さんのかけ声には「健康長寿」「家内安全」「虫歯撲滅」(歯科医院前)いろいろバリエーションがあって、お店の種類などによって変えているようでした。

17時頃までかかって街を回り、御射神社に戻ってきてようやく本祭りも終わりになります。
終わりに
以上、浅間温泉で実際に参加した経験をもとにした松明祭りのレポートでした。
ここまでご紹介した通り、松明作りや火の点け方、松明の引き方に、道具準備等…お祭りというのはすべてにおいて技術や順序、方法の伝承が不可欠です。
当然ほとんどの参加者が任意の参加ですから、積極的な文化の継承の成せる技というしかありません。
浅間温泉は現在少子高齢化が進み、お祭りを第一線でひっぱる70代の方々のあとを引き継ぐ次の世代はわずかです。
大きい松明を作る連も少なくなり、松明作りの技術の継承も危ぶまれます。
2019年の台風、2020年、2021年はコロナウイルスの為に、3年連続で松明祭りは中止になりました。
2022年の久々の開催では、色々を考慮し町会では連を作らないことに決まりました。
また、これまで参加していた大学のサークルの有志の連などは3年間中止になっていたおかげで新しい世代に受け継がれず途絶えてしまうようなことも起こり始めて、存続の危機が訪れています。
2022年の今回わたしが参加させてもらった連は、そんな松明祭りを後世へ繋げていくため、若手有志が集まった連です。
わたしは県外からの移住者で、さらに力がなくて主戦力としては動けませんが、こうしてネットで文化を発信することで浅間温泉の文化を残す為に少しでも貢献できればと思いこのページを作成しました。
こんなご時世でなかなかお祭りに参加するのも難しいですが、ぜひ落ち着いてお祭りが開催できるようになったら見学にいらしてください。
お祭りが盛り上がることも、文化の存続にとってとても重要なことです。
一見の価値あるすごいお祭りです。
見学にいらっしゃる場合は
「奇祭に挑む心構えと必需品」の項をよく読み、
興奮した悪気のない参加者に顔を煤で塗られるかもしれないこと、全身煙のすごい臭いになることをよくご承知のうえ、いらない服や靴を着用してのご見学をおすすめします。
浅間温泉の耳より情報
■浅間温泉下宿 篶竹荘(スズタケ荘)
ちょこが5年を過ごしたシェアハウス。
築年数100年近い古民家で、温泉入り放題が魅力的過ぎる。※詳しくは公式HPで
居心地は最高。
古民家が好き、浅間温泉の文化に触れてみたいという方はぜひ住んでみてください。
→公式HPはこちら
■「浅間温泉」写真散歩
いつもの浅間温泉を写真で紹介。
共同浴場、路地、旅館、古いお店新しいお店。
→「浅間温泉」写真散歩の記事はこちら
■あさま湯芽市
4月~12月頃に開催される、毎週日曜の朝市、木曜の夕市。
野菜や果物、穀物、はちみつ、パンなどいろいろなものが並ぶ楽しい市場。
→あさま湯芽市の日程や開催場所についてはこちら
■浅間温泉観光協会
浅間温泉の公式情報はこちらでチェック
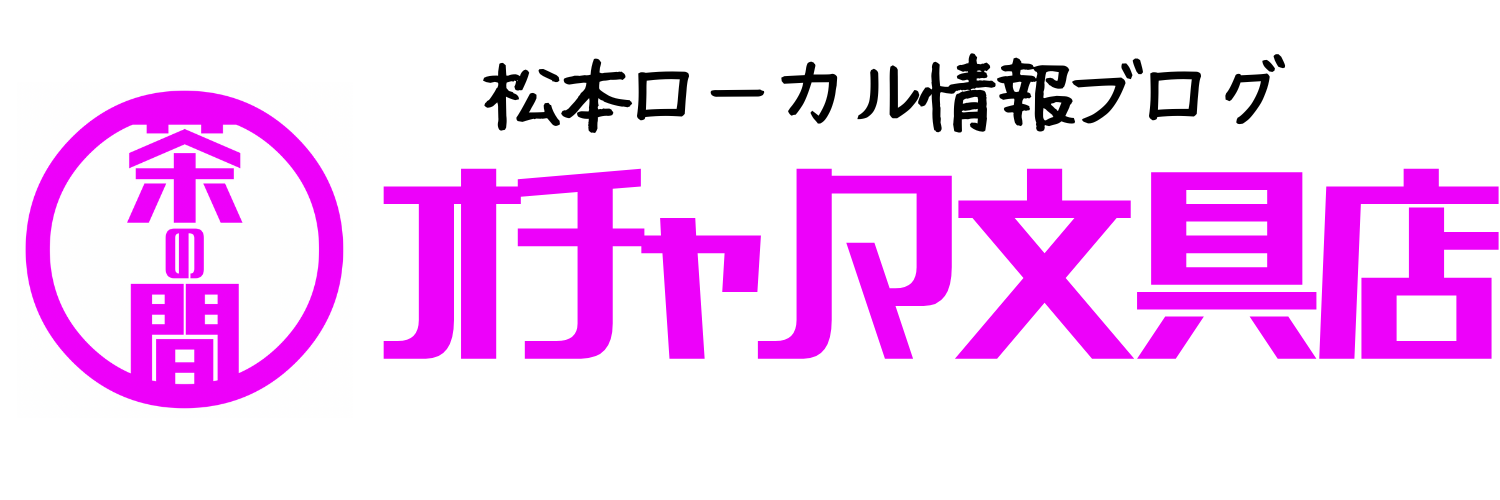



コメント