2022/7/29 加筆修正
こんにちは。
Chocoです。
遡ること数年前。
長野県松本市に引っ越してきて迎えた初めてのお盆に、わたしは数々のカルチャーショックを受けることになります。
見たことのないアイテムに聞いたことのない言葉たち。
しかし他人の家のお盆に参加させてもらうわけにもいかず、詳細は人から聞きかじるばかりではっきりとせず…。
月日は流れ、晴れて松本市ネイティブの男性と結婚したわたしは、ついに現地のリアルお盆に潜入することができました!
そんなわけで今回は、ようやく明らかになった松本市のお盆の風習について紹介したいと思います。

かんば
初めてのお盆でまず衝撃的だったのは、お盆を前にしたスーパーやコンビニで店頭に並べられた「かんば」という謎の…丸い物体。

どこへ行っても置いてある。
よくよく見ると木の皮がくるんと丸まったもの…なのか…?

いったいこれは何なのかとしげしげと眺めても何かまったくわからなかったこの「かんば」の正体は、お盆の迎え火送り火で火を焚く為のアイテム。
長野県のお盆では、多くの地域でそうされるようにきゅうりの馬とナスの牛(精霊馬と呼ぶんだそうですね)を作ります。
迎え盆の日は朝早くからお墓でかんば(白樺の皮)を焚いて(迎え火)その煙に乗ってご先祖様にお家まで帰ってきてもらいます。
提灯を持参して、お墓からかんばの火を家のお仏壇まで持って帰る家もあるんだそうな。

ヤニがたっぷり染み込んでいるので、火を点けるとあっという間に燃え上がります。

お盆最終日、送り盆の夕方にはお家の玄関先でかんばを焚いて(送り火)からお墓参りにいきます。
かんばの煙に乗ってご先祖様は帰っていきます。
天ぷら
最近わかったこととしては、なにかというと天ぷらを揚げまくるのが長野県民だということ。
お盆はもちろん、お彼岸やお葬式、お祝い事の席でも、とにかく人が集まるようなときには天ぷらを揚げる習慣があるような感じです。
それも、「天ぷらだけでお腹いっぱいにするのかな…?」という量の天ぷらを揚げます。
定番はご当地ちくわ「ビタミンちくわ」の天ぷらで、1本を2等分にした巨大な天ぷらが山のように積み上がります。
磯部揚げというものがありますが、ずいぶん雰囲気の違う食べ物です。

天ぷらまんじゅう
スーパーで初めて目撃したときには目を疑った「天ぷらまんじゅう」。
そう、長野県ではまんじゅうまで天ぷらにするのです。

こちらはネイティブの友人に教えてもらって一緒に作ったことがあります。
お盆やお彼岸の時期になると、スーパーで「天ぷらまんじゅう用まんじゅう」なるものが手に入るのでそれを使います。
「高遠(たかとお)まんじゅう」を使う場合もありますが、こちらは少し高価。
いずれもこしあんで皮が薄いのが良いのでしょう。
作り方は普通の天ぷら同様、天ぷら粉を水で溶いて、まんじゅうに絡ませて、揚げます。
調理中は不思議な気持ちになります。

ご想像通りヘビーなしろものですが、かりんとまんじゅうのような感じで普通に美味しいです。
時期にしか売られないので、おやつに2個入りを買ってきてよく食べてます。
調べてみたところ天ぷらまんじゅうは長野県全域で食べられているようで、塩やめんつゆを付けて食べたり、青じそを巻いて作る不可解なバージョンも発見…今度やってみるのでレポをお待ちください。
あらぼん
松本のあたりでは、身内に不幸があったあと、最初に迎えるお盆を新盆(あらぼん)と呼びます。
特別なことをするわけでもないようですが、近所の方や親戚などがお線香をあげにこられるようにお仏壇をしっかり準備したり家の中を整えるので、2回目以降のお盆とは区別して呼んでいるような感じです。
転んではいけない
お盆のお墓参りのときに、お義母さんに「お墓参りのときには転んではいけない」と聞きました。
「理由はわからないけど…昔からそう言うよ」とのことで、その理由がわからないというところが怖い気がして緊張しながら階段を下りました。
もしかしたらこれは長野県だけでなくて全国的に言われていることなのかもしれませんね。
松本の風習や文化
長野県に移住してきて驚いたのが、風習や文化がものすごく多く残っていること。
1年中そこら中でお祭りがあるし、お盆や年末年始は家族で過ごす習慣がある家庭が多い印象。
スーパーには行事ごとの謎食材が並びます。
オチャノマ文具店では他にも松本のいろいろな風習や文化を紹介しています。
現地で実際に見たり聞いたり参加した情報ですので、興味のある方はぜひのぞいてみてくださいね。
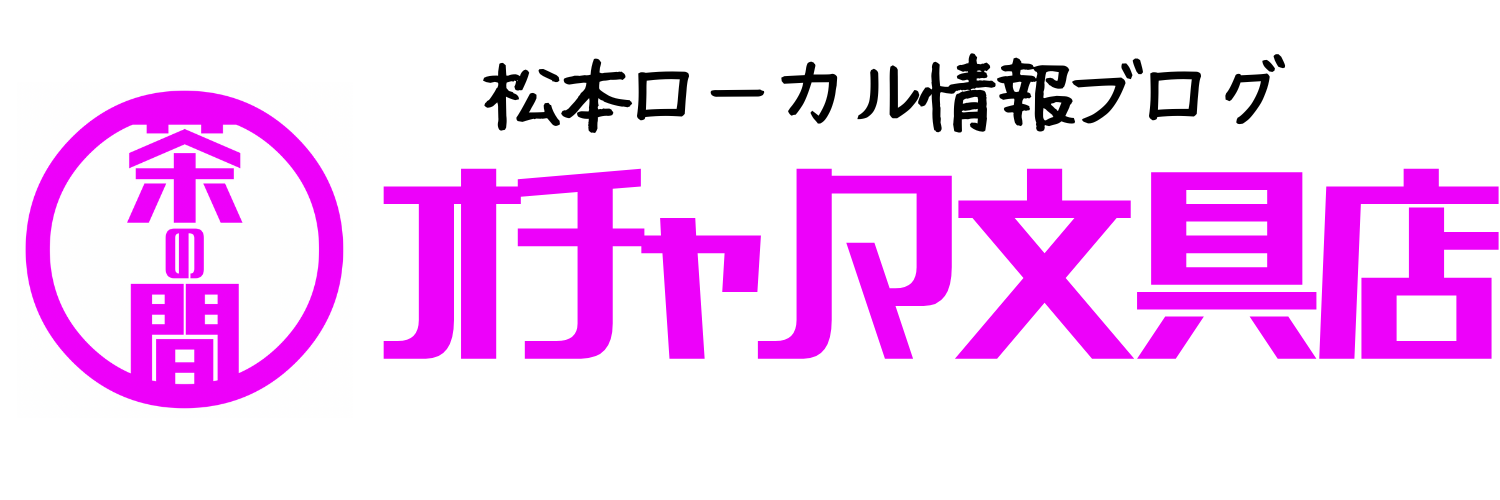



コメント