2022/6/5更新
こんにちは。
オチャノマ文具店のちょこです。
6月の季節行事といえば、梅仕事。
スーパーに並ぶ青々としたいい香りの梅を見ると、仕込みたくてうずうずしてきます。
だけど、毎年梅酒ばっかり作っても飲みきれないし、梅干や梅漬けは難しいし、面倒だし…
そんな話をしていたら、ヘルパーの訪問先のおばあちゃんが「簡単なのあるよ」と教えてくれたレシピが今回の【おばあちゃんのレシピ】です。
忙しくて時間がなくても、面倒くさがりでも、短時間で作れて数日で食べられます♪
おばあちゃんのレシピとは、
ちょこがヘルパーのお仕事先で利用者さんに教えてもらったレシピ。
80代や90代の利用者さんの、長年作り続けたレシピはどれも絶品。
簡単に作れる工夫や美味しく作るコツが盛り込まれています。
今回のレシピのポイント
・洗った梅の水分を拭き取らなくていい
・短時間でできる
・数日で食べられる

簡単煮梅の作り方
準備するもの
・青梅(南高梅かあまり小さくない梅がおすすめ)
・梅の8割の量の砂糖(梅1kgなら800g)
①青梅を洗って、ヘタを取る

ヘタはつまようじなどで取り除きます。
ヘタのところから雑菌がわくので、梅仕事においてこの工程は絶対に省略しないこと。

傷んでいる箇所があれば、包丁でカットしておきます。
②鍋に梅と砂糖と水少しを入れて、落とし蓋をして弱火で約20分煮る
砂糖の量は梅の重さの8割くらいの量を入れます。
砂糖控えめ…にすると、けっこう酸味が強くなるので注意です。

水の量は、砂糖が溶けて梅がひたひたになるくらい。
あまり水が多いとあとで煮詰めるのが大変ですし、少なすぎると灰汁が抜けきらない気がします。

ぶくぶくと灰汁が出てくるので、途中で取り除きます。
教えてくれたおばあちゃんは落とし蓋をしてほっとけばいいと仰っていたけど…ちょっと気になる量の灰汁なので…。

あまりぼこぼこ煮込むと梅が煮崩れるので、灰汁を取ったら弱火で優しく。
こんな感じで皮が透き通ってぷるんと柔らかそうになったらOK↓

③梅を保存容器に移し、残った煮汁を半量くらいまで煮詰める
梅を取り除いたあとの煮汁を、煮詰めます。
あとで保存容器の梅にかけたときに、ひたひたに漬かるくらいの量を残します。
煮詰めていると、煮汁がとろっとしてきます。

④煮汁を梅が入った保存容器に注ぐ
熱いうちに煮汁を梅の上からかけます。
数日寝かせて…完成。

今回は硬い青梅で作ったので、できたてでは渋い。
3日置いたらまろやかになりましたが、1週間くらいは寝かせた方が美味しいと思います。
完熟梅で作る場合は煮る時間は半分くらいでokで、できたてでも問題なく食べられました。
甘酸っぱいあんずみたいな味。
砂糖はお好みのものを。
黒いお砂糖で作るとコクのある味になります。
長期保存したい場合は、保存容器の煮沸消毒と脱気をしっかり行ってくださいね。
煮梅で梅雨を乗り切る
松本では、梅仕事と同時に、じめじめした梅雨がやってきます。
夏の兆候のように急に30度近い暑さがやってきたかと思った矢先の梅雨入りで、低気圧と気温差にやられて体がだるーくおもーくなる季節ではないでしょうか。
うちでは毎年このできたての梅煮を食べて、なんとか梅雨を乗り切ります。
この酸味と甘さが、なんだかきく!
毎日1粒づつ…と大事に食べているうちに、同時に仕込んでおいた梅シロップも出来上がって、真夏には梅ジュースで喉を潤します。

煮汁ごとヨーグルトにかけて食べてもいいですし、そのままパクっと食べるのも美味しい。
少量の梅からでも気軽に作れるので、ぜひ試してみてくださいね。
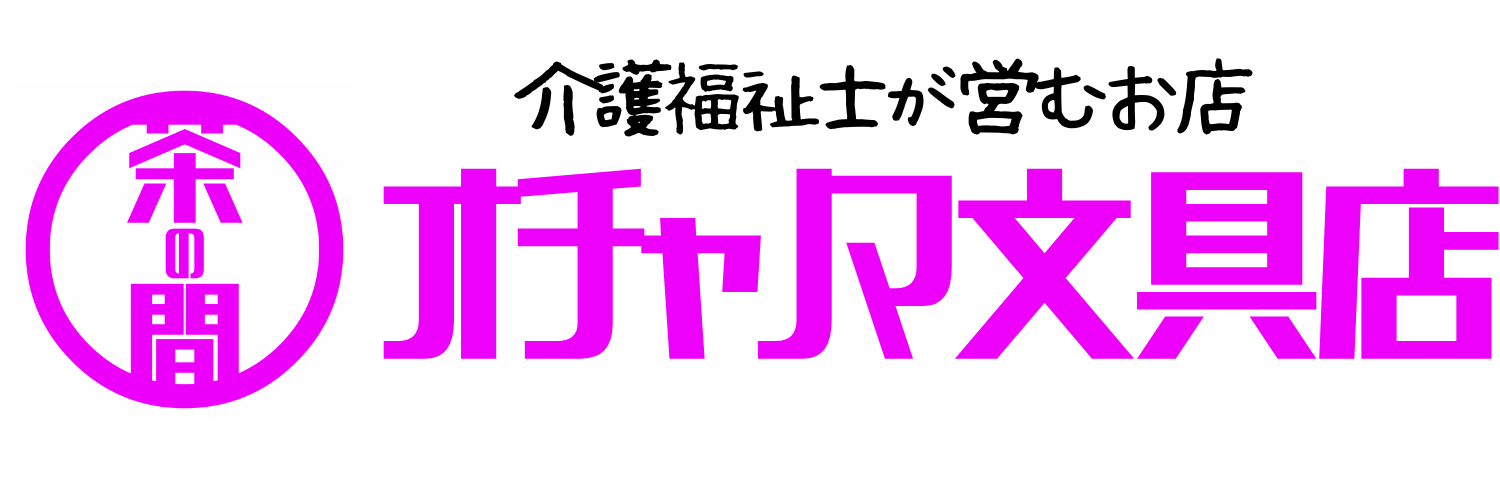






コメント