こんにちは。
オチャノマ文具店のちょこです。
信州といえば野沢菜(のざわな)の漬物。
こちらではみんな自分の家で漬けます。
松本に初めて来たとき、世界にはこんなに美味しい漬物が存在するのか、と震えたくらい!手作りの野沢菜漬けは美味しいんです。
それぞれの家の味があって、お土産屋さんで売られているものとは全く別物の絶品。
わたしも何度か挑戦してみましたが、大きなタルで漬ける本漬けは経験と技術が必要で美味しく作るのはすごく難しい。
それでも手軽に美味しい野沢菜漬けを作りたい!という方のために、今回はわたしのような初心者でも失敗なく簡単に作れる「野沢菜の切り漬け」の作りかたを紹介します。
このレシピのポイント
・簡単
・少量から漬けられる
・1週間くらいですぐ食べられる
このレシピは、訪問介護の利用者さんに教えてもらった【おばあちゃんのレシピ】です。
おばあちゃんのレシピとは、
ちょこがヘルパーのお仕事先で利用者さんに教えてもらったレシピ。
80代や90代の利用者さんの、長年作り続けたレシピはどれも絶品。
簡単に作れる工夫や美味しく作るコツが盛り込まれています。

野沢菜とは
野沢菜は長さ60cm~80cmくらい。
長い小松菜みたいな感じですが、茎がしっかり根本にいくほど太くなります。
もともとは南の方から入ってきたカブの一種で、根っこを食べるつもりだったのがあまりに寒すぎて上にばっかり伸びた結果こういう野菜になってしまったんだとか。
野沢菜の出回る季節
冬の寒さが本格的になってくる頃、松本では八百屋や産直所で野沢菜が出回り始めます。
自分の畑で育てている方も珍しくありません。
地元の方が言うには、一度雪をかぶってから収穫したものの方が柔らかくなるんだそう。
なので、みんなすぐには買わず美味しくなる頃合いをじっと待ちます。

風物詩「お菜洗い」
信州では大量の野沢菜を最初に洗う工程のことを、「お菜洗い」と呼び、この時期の季節行事みたいになっています。
松本で「お菜(おな)」と簡単に呼ぶ場合、これは菜っ葉ではなく野沢菜のことを指すんですね。
長野県内でも北に位置する野沢温泉では、温泉のお湯でいっせいに野沢菜を洗うところが有名で、毎年ニュースになります。
松本では凍えながら水で洗います。
今回の切り漬けを教えてくださったおばあちゃんは、豪快にお風呂場のシャワーで洗っていました。

野沢菜切り漬け
野沢菜の切り漬けは、少量から手軽に漬けられる、浅漬けのようなもの。
漬けて1週間も経てば食べられます。
松本では時間のかかる本漬けが漬かるまでの間は、この切り漬けを作って食べます。
「時漬け(ときづけ)」と呼ぶこともあるようです。
また、本漬けのように大量に仕込まなくても美味しくできるので、スーパーで1束だけ買ってきて漬けられます。
作り方
①野沢菜を根本まできれいに洗う
根本まで土が残らないように、しっかり洗います。
傷んでいる部分は取り除いておきます。

②5cmくらいづつにカットする
野沢菜を丸ごと漬ける本漬けに対して、「切り漬け」と呼ばれるのは、食べやすい大きさにカットしてから漬けるから。
根本の太いところは、切り落とさず切れ込みを入れておけば食べられます。

④食品保存袋に入れて、料理酒を少し入れて振る
ジップロックなどの密封できる保存袋に、②の野沢菜と酒を少し(大さじ1くらい)入れます。
袋を閉じて、全体に酒が回るように振ります。
おばあちゃんによると、お酒は別に入れなくてもいいけど、自分はいつもこうしている、とのことで。
美味しくなるからか、傷みにくくする為か、理由はわかりませんがとりあえず真似しています。
③に塩少々・醤油・砂糖・塩昆布を入れてよく揉む。
③の袋の中に、塩少々・醤油・砂糖・塩昆布を入れてよくもみます。
おばあちゃんに教えてもらった各調味料の分量は「適当!」と…
大体のおばあちゃんのレシピは「調味料の量は適当」と言われるので自分で加減して覚えていますが、大体の目安としては
野沢菜500gに対して
・塩 小さじ1
・砂糖山盛り大さじ2
・醤油100ml
・塩昆布 ひと掴み
くらいで作っています。
わたしは甘めが好きなので、砂糖多めです。

塩昆布がなければ昆布茶でも代用OK。
なくても作れますが、わたしは昆布入りの出汁が効いた味が好きなのでいつも入れます。

次の日になっても水分が全然出てこない場合は、調味料が足りません。
えぐみが強くなってしまうので、途中でもいいからお醤油を足しましょう。

ポイントは、袋の上からしっかりよく揉むこと。
こうすることで味が染み込みやすくなるのと、水分が出やすくなってより早い時間で漬かります。

冷蔵庫で寝かせて、1週間くらいから食べられます。
熟練の技術が必要な本漬け
野沢菜をまるごと使う本漬けは、ある程度大きなタルで漬けます。
失敗すると心と財布のダメージが大きく、温度の安定した保管場所も必要なのでアパートなどではちょっと難しいかも。
最近は松本でも大量に漬ける家は減ってきたようですが、それでもみんな巨大なタルにひとつくらいは平気で漬けています。

本漬けは野沢菜を丸ごとタルに詰めて、調味料と交互に重ねていきます。
家によって調味は様々。
シンプルに塩のみ、という家もあれば、ざらめと醤油とか、にぼし粉や柿の皮をプラスしたりする場合も。
漬かる過程で発酵するので、時間がかかるし傷まないような調味のさじ加減が必要です。
上手に漬ける方は塩だけだなんて信じられないくらいとびきり美味しく仕上げるのですが、これが難しいわけです。

「塩は霜降りにかけるんだよ」と教えていただいて、3度チャレンジしたことがありますが、その「霜降り」とやらが難しくて…
いまだ一度も美味しく作れたことがありません…。
しっかり発酵させて作った野沢菜は、少しづつ取り出して冬中食べます。
タルから出した瞬間に味が変わり始めるので、その日々の変化も楽しみのうち。
春先になって酸っぱくなってくると、塩抜きをしてから油炒めにして食べるのですが、これもすごく美味しいのです。
寒くなるまでに採れた野菜を、作物のとれない冬の間長く保存しながら無駄なく食べる。
生活の中から生まれた知恵には頭が下がります。
信州に来たらぜひ本当の野沢菜を
信州に来ることがあったら、ぜひお蕎麦屋さんや、何なら地元の方をつかまえて手作りの野沢菜を食べてみてください。
お土産用の野沢菜とは全然違う美味しさに感動するはず。
ちなみに、お土産に買うならスーパーの要冷蔵のものがおすすめです。
真夏は持ち帰るのが難しいかもしれませんが、やはり地元の人が食べているものが本場の味ですから。
わたしも…、信州人になったからには美味しく漬けられるようにがんばります!
松本のご当地食
【牛乳パンが一瞬でリッチなスイーツになる魔法】はこちら↓
【冬至の郷土食かぼちゃだんご】はこちら↓
【わさびの花の食べ方 ツーンと辛くする方法】はこちら↓
【まんじゅうまで天ぷらに…】はこちら↓
信州のご当地食品いろいろ試してみてくださいね♪
ここまで読んでいただきありがとうございました。
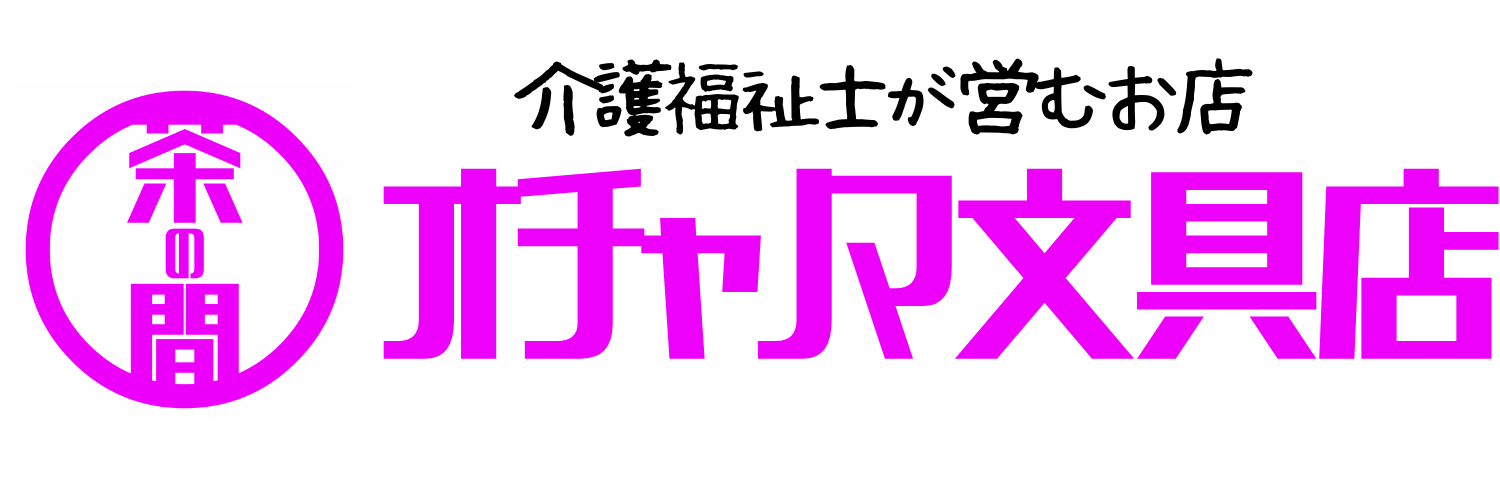









コメント